障害者グループホームの裏側で進行する「福祉ビジネス」の闇とは? – あなたの知らない「静かなる虐待」
皆さん、こんにちは!
今回は、私たちが普段あまり目にすることのない、グループホームという場所で起きている経済的虐待の実態、そしてその背後にある「福祉ビジネス」といういびつな構造に深く切り込んでいきたいと思います。
一見、利用者さんの生活を支える大切な場所に見えるグループホームですが、残念ながら、その裏側には利用者さんの財産を蝕む「静かなる虐待」が潜んでいることがあります。
——————————————————————————–
1. 利用者さんの「お金」が消える!? – 信じがたい横領の実態
実際にあった衝撃的な事例からお話ししましょう。
あるグループホームで、複数の利用者さんの工賃(給与)が、銀行口座に入れると言われたにもかかわらず実際には入っておらず、合計で100万円単位のお金がどこかに消えていることが判明しました。これは、当時の管理者だけが現金と通帳を管理する金庫を扱っており、その管理者が退職した際に金庫の中身がゼロだったことで発覚しました。
これは紛れもなく、障害者に対する「経済的虐待」に当たるとされています。他のケースでは、利用者一人から30万円以上が消えたという情報もあります。過去には、株式会社恵というグループホーム運営会社で、食材費を水増しして利用者から徴収する組織的な経済的虐待が発覚した事例もありました
。
このようなお金の横領は、身体的暴力や暴言とは異なり、利用者さんに気づかれにくい「静かな虐待」と表現されます。管理者が「今いくらありますか?」と聞かれても、「まだこれだけしかないよ」と嘘をつき、利用者さんはそれを信じてしまう可能性があります。
——————————————————————————–
2. なぜ「静かなる虐待」が起きるのか? – 構造的な問題と「福祉ビジネス」のからくり
この経済的虐待の背後には、複数の深刻な構造的な問題が横たわっています。
• 監督体制の欠如と信頼の悪用
◦ 驚くべきことに、グループホームには利用者さんの財産を預かる法的義務がありません。これはあくまで「善意による無料サービス」とされており、行政の定期チェックである「実地指導」の対象外であるため、お金の管理に対する監督体制がほとんどありません。
◦ 利用者さんは生活の場であるグループホームの職員を信じ切り、「お金預かりますよ、管理しますよ」と言われると、まさか横領されるとは思わないため、チェックがしにくい状況にあります。このため、「頭がいい人だったらやれちゃう」状況であり、「どこのグループホームでも多分起きている」と指摘されています。
◦ 職員や支援者は「他人」であり、自分しか管理しない状況だと、他人の財産を見て「欲しくなっちゃう」可能性があるとも言われています。
• 組織的な隠蔽と対応の遅れ
◦ 経済的虐待が発覚しても、運営会社が「穏便に解決する方法」を模索し、決着を4ヶ月以上も先延ばしにしている事例があります。これは、噂が広まって利用者が退去し、会社の売上が下がり潰れることを懸念しているためだと考えられています。
◦ 結果として、お金を横領された当事者には事実が知らされないまま放置されるという、矛盾した状況が生じています。
• 「福祉ビジネス」のいびつなからくり
◦ さらに深い問題として、障害福祉の制度には、利用者にメリットがないにもかかわらず、事業者が利益を得られる「からくり」が存在すると指摘されています。
◦ 例えば、B型事業所の国からの補助金は、利用者へ支払う工賃の平均値が高いほど増額される仕組みがあります。事業者は、利用者から徴収した弁当代などを工賃に上乗せして支払うことで、見かけ上の平均工賃を上げて国からの補助金を何十万円も増やしながら、利用者が実際に受け取る作業分の額は変えないという「テクニック」を使っています。
◦ これにより、潤うのは会社だけで、**利用者は「一切メリットが発生しない」**状況が生じています。フランチャイズ本部がこのような「儲かる方法」を指導しているケースもあるとされ、福祉業界で「利益が薄い」と言われつつも、やり方によっては利益が倍になるという実態が「福祉ビジネス」として存在しています。
◦ このような状況は、本来利用者をサポートするための制度が、逆に「虐待じみたこと」につながる「いびつな」ものであると批判されています。
• 職員の質と研修の形骸化
◦ 福祉の業界には、他の会社で馴染めなかった人や、過去に横領などの問題を起こした人が流れ着いている可能性も示唆されています。
◦ グループホームの全ての職員は虐待予防研修を受けることが義務付けられていますが、実際にお金がなくなる事態が発生していることから、研修が機能していない現状が示唆されています。
——————————————————————————–
3. 利用者さんとご家族にできること – 自己防衛の重要性
このような実態があるからこそ、利用者さんとそのご家族には、自分の財産を守るための行動が強く求められます。
• 定期的な金銭のチェックを!
◦ もしグループホームにお金を預けているのであれば、月に1回は必ず「今、お金はどれだけありますか?」と確認し、現金を見せてもらうなどして、定期的に残高を確認することをお勧めします
。通帳の記帳も定期的に行いましょう。
• 支援者を「疑う」視点も必要
◦ 「福祉の人たちは良い人ばかり」という思い込みは危険です。残念ながら、「ずる賢いやつはいる」という現実を受け止め、支援者に対しても適度な警戒心を持つことが、自己防衛につながります。
◦ 「スリッパがない」「アイテムを変えられない」「お金を引き出してもらえない」といった異変を感じた場合は、疑って確認することが重要です。
福祉は、本来、利用者さんをサポートするためのものです。しかし、その制度の歪みや事業者の利益追求が、利用者さんを犠牲にする「福祉ビジネス」を生み出してしまっている現実があります。この「いびつな」状況を変えるためには、私たち一人ひとりが現状を知り、声を上げていくことが必要です。
利用者さんが安心して生活できる環境を、社会全体で築いていきたいですね。







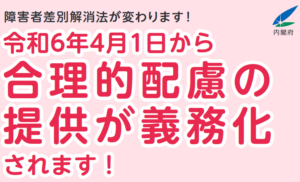

コメント